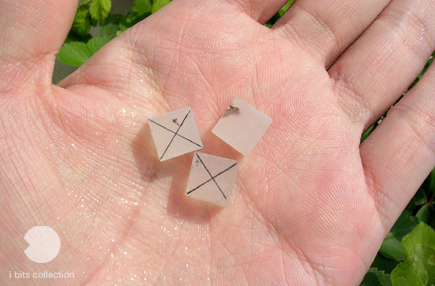多くの人の“大切なわたしのかけら”となることを願いまして…
collaborate
作品カテゴリ一覧
ショッピングカート
カートの中身
カートは空です。
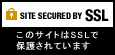
|
ホーム |
作者の思考
作者の思考
作者の思考:852件
素朴な疑問
作品紹介
河川モニターの返答
作品紹介
作品紹介
少子化の実態を考える
作品紹介
作品紹介
河川モニター
作品紹介
約束の地に
作品紹介
河川モニターの返答
作品紹介
お守りの原点
モニター活動
作品紹介
奴奈川の勾玉
丸玉の制作
競争と闘争
|
ホームページ作成とショッピングカート付きネットショップ開業サービス