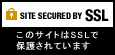2015年02月20日
以前にも書いた糸魚川翡翠の未来を、再度考えてみました。(何度目だろうか(笑))
今月の13日から、物産センターの内装工事が始まっています。
工事と言っても今から始めるような小規模な工事で、一部の壁を壊したり作ったりする程度です。
商品の並び替えもするようですが、どうもスーパーマーケットのような並びになるらしいです…。
これ以上、糸魚川翡翠の品格を落として欲しくないなあ…。(噂なので、最終的な形に成らないと何とも言えないのですが…)
工事の為、商品ブースの簡易的な移動をしていますので、私のブース周りが少し混沌となっていますが、3月8日には終わるとの事なので、ご了承下さい。
この移動に伴い私のブースが何処へ置かれるのか、一抹の不安がありますが…。(まぁ、現場には臨機応変に対応してもらいますけど(笑))
どうしても糸魚川翡翠を別格の扱いにせず、物産の領域に留めたいようで、自分達が扱えるように存在を引き下げている感があります。(消耗品の扱いにしたいのでしょう)
更に産地を明確にする事もなく、業者を明記する事も無いようです。
要はミャンマー産翡翠を扱う事を、黙認したいのでしょうね。
糸魚川だけは「糸魚川翡翠しか扱わない」とした方が、世界に認めてもらえるのに…。
未だに「安く仕入れて高く売る事」を考えているのだろうか?
これに迷惑するのは、お客さんは勿論ですが、相対する販売員も対応に困ります。
どこの産地なのかも解らないまま、対応しなくてはならないのですから…。
現場の人達に手を汚させ、自分達は隠れて手を汚さない、そんな卑怯な事をこれからも続けて行くのだろうか?(そして知らなかったと逃げるのだろうか…)
しかも銀行から天下りしたジイさんを、引き続き加工所に入れていくようなので、翡翠好きの人達にちゃんと対応する気も無いようです。(銀行から融資を受ける為の施設になっている気がする…)
これが今の経営陣の限界なのだろうか?、どうにも改善不可能な現状が、今の糸魚川には存在しているって事なのだろうか?
市で翡翠をメインの一つとすると明言しているのに、何故こうも現状(中身)が追い付かないのかな…。
来客数(名)だけを考える公僕は今更どうにもなりませんが、利益(実)を考える業者の準備が全くできていません。(実を考えられないから、公僕なんですよね(笑))
現在の商売に必用なのは「福沢諭吉の印刷物を集めて喜んでいるだけの者達」では無く、それらを適度に使ってモノに変える人達なわけです。
お金を交換券として使える人達、汚く稼いだとしても綺麗に使える者達、商売に必用なのはそういった人達となります。
しかし糸魚川の翡翠には、綺麗に使える領域が少なすぎます。
同じように汚く稼ごうとしている者達で溢れ返っています。(その者達は、得たお金を綺麗に使う事はありません)
どうも「根本的な破綻」が存在しているのだと、改めて感じます。(中身のないパフォーマンスが多すぎますね…)
将来的に考えれば、糸魚川の翡翠を扱う者は「作る側である」って事が不可欠です。(ライセンス制も必用かと)
翡翠を仕入れして売る業者は、外で撃ちまくっていれば良いでしょう。
戦争と同じで「他人の国で争いたがる」って事が、最大の共通点でもあるのだから…。
そして作る側は、物産の加工所や高浪の池、不動滝などの管理を一部担う必用があるでしょう。(地域の人と財源を別にして、ローテーションで定期的に担う)
ああいった観光スポットは高齢化により、担い手不足になっていきます。
要は「観光に関わる仕事に協力する必用がある」って事で、家にこもって加工していれば言いわけではありません。(引きこもりじゃ無いのだから)
それと糸魚川での遺跡調査にも、協力していく必要があるでしょう。(糸魚川には、調査を目的とした遺跡発掘が必用かと)
糸魚川へ遊びに来た自身のお客さんを名所に案内しながらも、初めて来るお客さんとも楽しみを共有する、そんな活動が糸魚川翡翠を扱う者に求める「最低限の条件」にして行く必用があるでしょう。(主にフリーのお客さんが対象で、団体は業者に任せるのが良いかと)
ただ、基本的にサービス業ではないので、お互いに礼節をもって楽しめたらと思います。
もちろんこれには、翡翠だけの売上げで生きて行く事のデメリットの解消にもなります。(財源の確保が最優先ですが)
翡翠にとってのデメリットは「過剰に消費される事」であり、作り手としてのデメリットは「他者に足元を見られる事」ですから…。
また、今現在の糸魚川での「売る側と買う側の考え」を極端に説明すると、売る側は「安く仕入れたミャンマー産翡翠(処理品)を高く売りたい」って事で、買う側は「良質な糸魚川産翡翠を安く購入したい」って事です。
ここまでお互いの要望が離れていては、どうにも近づく事はできません。
なので「糸魚川産翡翠を適正価格で売る(買う)」と言う事が、求められるでしょう。
それを可能にするのも作る側であり、この者達の教育、或いは選別が絶対条件となります。
これには「信念を持った人材」で、団結する事が望ましいと考えます。(職人モドキでは無く)
ちなみに本来なら糸魚川の翡翠原石(特に切断されている原石)は、市がライセンスを持った加工人に販売して財源にするのが一番理想的だと考えます。(糸魚川翡翠の全てが、国の天然記念物に指定されている訳では無い)
では原石はどう揃えるのか?、ですが、市民に寄付して貰えば良いのです。(寄付した人に、ふるさと納税のような優遇処置をするのも良いかと)
これには、一定のレベルの翡翠原石である必用があります。
誰も寄付しないと思うかも知れませんが、それは田舎を知らない人の考えであり、その気があるか無いかの問題では無く「そうせざるを得ない」って状況に成るのが田舎の集団心理なわけです。
要は、ただ翡翠原石を持っている者は「住みづらくなる」って事で、幾つかを寄付する事で免罪符の役割を果たすわけですね(笑)
例え原石をライセンス所有者に販売しても、それを他者に売るライセンス所有者が現れるのでは?、と言った懸念もありますが、ちゃんと記録を残せば問題ありません。
その原石で何を作ったのか、残りのプレートはどれだけ在るのか、などを記録で残します。
原石を欲しがる者の殆どが「原石のままの姿での所有」を望むので、一度切断してしまえば需要は無くなります。(プレートにすれば、管理も簡単ですし)
もしそのプレートを誰かに売ったとしても分かるし、他者がそのプレートで制作した商品を売るにも糸魚川の外でしか売れなくなります。(要は趣味で加工する人達にしか売れないって事で、大した利益になりません)
勿論、その事がバレたらライセンスは没収となりますので、そこまでしてやるメリットもないわけです。(完全には防げませんが、かなりの抑止力になり、人格の問題にもなるので大丈夫かと…)
重要な事は、これは市に寄付され、市から購入した翡翠原石(主に切断された原石)での話であり、海や川で拾った翡翠などには適応されません。
この事は糸魚川翡翠を消費する事への「正当性を示す行為」でもあり、「戒め」でもある重要な大義名分になるかと私は考えています。
そんな事をしなくても翡翠販売業者の売上げを上げて税金を増やせば?、と思う人もいるでしょうが、そんな大規模な会社には成り得ませんし、成る必用も在りません(笑)
石灰石とは訳が違うので、その道理は通用しないでしょう。(でも市で石灰石を売っているのだから、市が糸魚川翡翠を売れない道理も無い訳です(笑))
どうしても未来の翡翠の加工人には、胸を張って生きてもらいたいんですよね…。(このままでは、ただの無頼漢にしか見えないし)
ここに書いた事は私個人の考えなので、各々が糸魚川へ来て自分の目で判断すると良いでしょう。
でも判断できるだけの基準を持っていなければ、上っ面に騙されるのは間違いないので、意味ありませんけどね(笑)
それにこれは、もっと先の「未来のカタチ」を想い描いての話なので、メンツが揃わない今では無理な話なのでしょう。
結局は自分の信じている姿を、見せて行くしか方法は無いかと…。
でも見せても「同じ事が出来ない」と言うのであれば、同じ事のできる者が現れるまで待つしかないのかもしれません…。
でも確実に前に進んでいるのだから、今は自分の事を頑張りたいと思います。