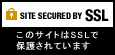2020年05月30日
芽吹きの季節は終わり梅雨の季節(躍動の前段階の季節)を向かえます。
本来なら大型連休の疲れを癒すタイミングですが、今年はコロナショックの影響で「別の意味での疲弊」を癒す時期になりそうです。(精神的な疲弊を癒す時期かと)
これからどうなっていくのかは解りませんが、やれる事は進めて見極めて行きたいと思います。(予想は出来るので、準備はしておきます)
それでは5月終盤の探石記録をまとめて書きます。
この日は午前中が晴れていましたが、午後から次第に曇ってきました。(5/26)
平日ではありましたが数人が訪れていて、それぞれに海辺を楽しんでいました。
先日の24日(日曜日)は賑わっていたようで、多くの車が止まっているのを確認しました。(こういう時は邪魔にならないよう、探石を控えています(笑))


浜は波が弱く濁りもない状態、小さめの石が多く上がっていました。
それでも水底の石を確認する事ができたので、探し甲斐のある環境ではありました。
ただ、曇天気味の天気により目の上が重く感じ、乏しい光源での探石は普段より疲れました。(やはり晴天での探石が一番です)

一通り歩き折り返し地点に到着、探し始めよりは明るくなりましたが、能生方面も霞んだ空に覆われたままでした。
しかしデメリットだけではなく、直射日光が遮られたお陰で厳しい暑さからは守られました(笑)

この日に見付けられたのは、ネフライト(大小)2個だけでした。

大きいネフライトは良質、中の上クラスかな〜、磨けば綺麗に仕上がると思います。
発色も黒ずんでいないので透明感があり、目立ったヒビもないので加工素材としても使えるかと思います。(とりあえずは、そのまま磨きます)
今回の微睡んだような景色は「今現在の人間社会」を映しているようで、この晴れも曇りもしないメリハリのない環境は人の心を暗くするようです。
気晴らしとしては不十分だったなぁ…、いや、この1個があっただけでも幸い、来た甲斐があったと言うものです。(美しい石たちが、私に一筋の光明を見出させてくれます)
手にした成果を素直に喜びたいと思います。
そして2日後、前回の暗い天気を払拭するかのような晴天が広がりました。(5/28)
目に映る全ての色が輝きに満ちている、最高の探石日和です!
青空に浮かぶ雲も、喜びで躍っているかのようでした。(個人的感想)

普段より遅い午後1時頃からの探石、陽が長くなった事が嬉しく感じました。
浜は波がやや強かったですが、透明度を増した海では水底を確認する事ができました。
晴天の割には風が冷たく、探石の最中に汗をかく事はありませんでした。(心地良い風でした)

濁流だった姫川はヒスイ色へと変わり、豊富な水量で本流を満たしていました。
思わず飛び込みたくなる美しさ、しかし恐ろしさも兼ねているので実践すると瞬く間に冥土へ直行となります。


この時点で見付けたのは、ロディン岩(鶯石)2個、緑色石英(キツネ石)1個、ヒスイ転石1個です。

パッと見てヒスイ転石が最もヒスイに見えないなぁ…、拾い上げ乾かして吟味するまでチャートとの見分けがつかなかったし(笑)
とりあえず上のロディン岩(鶯石)は、大きい方は発色が良いですが石質は良くありません。
小さい方が良質なので、大きい方は海に返しました。(砕けて研削・研磨された後に再び会えたらラッキーです)
緑色石英(キツネ石)は、珪化が強いと言うよりは母体が石英多めのタイプで、磨けば綺麗になりそうだったので拾いました。(試してみます)
ヒスイ転石は、最初に書いたようにチャートにそっくり(笑)
これは青銅色を示したりするオンファス系の特徴で、くすんだ淡い碧色(灰色)に見える部分には翡翠輝石を確認する事ができます。
濃い碧色部分は光沢を示すので、チャートとの区別は乾かしてから観察すると良いです。
ちなみに、このタイプのヒスイは透明度は皆無ですが光沢が抜群に出てピカピカになります。
帰り際では、小さめの緑色石英(キツネ石)1個、ロディン岩(鶯石)1個を発見。

この緑色石英(キツネ石)は発色がヒスイに似ているタイプ、石質も良くチャートに似た質感で柔らかい光沢も示したりします。
裏側には茶色の筋が見られ益々紛らわしい…、「キツネ石と言われる由来」を備えたタイプなので見本には良いかと思います。(ヒスイと比べた由来であり、石本体の由来ではない)
ロディン岩(鶯石)は、でべそ部分が黄緑を示しています(笑)
サンプルとしては良いサイズと発色、白い部分にはソーダ珪灰石が混ざっているのかな?
純粋なロディン岩は白なのだろうか?、とも考えたのですが、岩石なので純粋もなにもないですね(笑)
ゾイサイトが多めなのか、ソーダ珪灰石が多めなのか、ってくらいの違いなのだろうか?
最後は姿が魅力的な梅輪石、鉱物としては玄武岩だったかな?

何故か惹かれる姿をしていたので手に取りました。
丸みがあって、凹んでいて、白い斑点があって、座りが良くて、手の平サイズで、色々と可愛らしい(笑)
ヒスイの魅力のような「揺るぎない力強さ」ではなく、素朴で落ち着く感じ、この自然研削・自然研磨が絶妙なのでしょう。
ヒスイ転石にも肉球みたいな癒しの姿があり(押上での転石に)、それに通じた魅力を備えながら侘び・寂びの世界にも通じている感じ、うまく説明できないけど「民芸」って感じです。
とにかく面白いので持ち帰り飾って楽しみます(笑)
5月も楽しい時間を過ごせました、今ほど糸魚川に移り住んで良かったと感じる事はないでしょう。
完璧な幻想逃避(人間社会からの逃避)ですね(笑)
生きる上での経済的な事からは逃げ切れませんが、どれだけ逼迫しても人の世からお金が消えた事は唯の一度もないので、そこから逃げる事は考えず正面から向き合いたいと思います。(誘導される事なく、自身の頭で決断したい)
これで今回の探石記録を終わります。
6月からは物産センターで石の簡易的な識別を始めたいと思います。
基本的に土日のどちらかは常駐したいと思っています、雇われているお爺さんがいない日に代わりに居る感じなので、平日でも何かしら作業していると思います(笑)
個人的には「賑わいに左右されないスタイル」を目指してやってきました。
この仕事は大勢を相手にする仕事ではないので、自分に必用となる人たちを見極めながら今までやってきました。(支えてくれた皆さんに感謝です!)
しかし、全く大量消費の恩恵を受けていなかった訳でもないと思いますので、これからの体験は貴重なデータとなると思います。(現に独立したばかりの年の売上げレベルに落ちているし…)
この時期を延命に専念するのならば、その先の未来を示さなくては死に金になります。
「遅かれ早かれ」って状態になってしまったら遅すぎる…、その前段階での行動が揺るぎない未来を示す証明となり、生き金とする唯一の方法だとも言えます。
良く考えて生きなければなりません。
とにかく、まずは石の簡易的な識別、この行動に報酬は発生していません。
物産センターも「それどころではない」って状態なので、そんな時期に請求できないです(笑)
それに本音を言えば「束縛されたくない」って事もあるので、自分のペースで行いたいと思います。
穿孔や切断は加工所として受けて手伝いますが、その他の委託加工は私の場合だとオーダーメイドになるので料金が跳ね上がります。
よって通常の委託加工は、お爺さんに依頼するのが良いかと思います。
密集する事を注意しなくてはなりませんが、14年前でも識別で並ぶ事などはありませんでした。
フォッサマグナミュージアムでの識別は「仕掛けが大がかり」だったのでしょう。
夏休みに向けたイベントだったし、国石となった時だったし、何よりもコロナウイルスが発生していなかったので大行列になったのだと思います。
なので、そこまで心配する事もないかと思っています。(今現在、ほとんど人がいないし)
注意点としてマスクは着用して下さい、後は物産センターで買い物もして下さい。(ジュースやアイス程度でも良いです)
学者じゃないので解らない石もあります(笑)、いない日もありますので悪しからず。
これは作家としての活動と言うよりは、加工所の未来の活用を考えての事なので、作家として支える場合は作品を買って下さいね。(先日に購入して頂いた方、改めて有り難うございました!)
在るべき姿は見えていますが、そこまで辿り着くのに試練が多すぎる…。
これが40代の試練か…、まさに千波万波だな…、「乗り越えてやろうじゃないか!」って程に若くはないですが、迂回する道も無いので木っ端微塵になるまで進みたいと思います(笑)
今年は夏から秋が正念場となるでしょう。
賑わいの恩恵を受けずに生きる方法を確立するのか、再び大量生産・大量消費に戻そうとするのか、世の中の動向も見ながら慎重に進めたいと思います。(私の仕事は性質上、前者に進んで行くのですけれど…)
なんであれ、覚悟を決めて行動したいと思います。