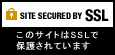2020年02月13日
日に日に春を感じる気温になっていますが、観光を楽しむ人たちの訪れは未だ遠いようです。
毎年12月〜3月までは「ほぼ冬眠しているまち」ではありますが、今年は見えない驚異(コロナウイルス)により、今後の景気にも影響がありそうで心配です。
でも心配したところでどうにもなりませんので、理想のカタチを目指して準備したいと思います。
それでは2月四回目の探石記録を書きます。
前回から1日しか経っていませんが、朝から晴れたので押上の海岸へ行きました(笑)
午前10時頃の海岸、空は晴れ渡り無風、引き潮で波はこの時期としては弱めでした。
7日に見られた雪も無くなり、完全に春の海辺となりました。(2/12)


いつものように左側から探石。
浜辺は砂が多かったですが、進むに連れて押し上がった石たちが姿を見せました。
太陽光で気温は上がり、体感として4月くらいの暖かさでした。(無風だったからかな?)

まさに探石日和、これで良い出逢いがあったなら最高だと言えます。
やや押し上がった浜を歩き折り返し地点に到着、強めの太陽光で石たちが輝きまくって目が痛くなりました(笑)

この時点では石英斑岩3個、玉髄(メノウ)1個、ネフライト1個、ヒスイ転石3個、ビー玉1個(笑)、ロディン岩1個、緑色石英(キツネ石)1個、オンファス輝石1個を見付けました。

石英斑岩は薬石タイプ、小さくて綺麗なのを優先します。
玉髄は縞瑪瑙と言えるタイプ、「カルセドニー」ではなく「アゲート」と言えるでしょう。
ネフライトは通常の小判形タイプ、薄い部分は光に透けて綺麗です。(乾くと表面が白くなる)
ヒスイ転石は白ヒスイと右の小さいヒスイに翡翠輝石が見られます。
下のはちょっと混ざりがあるので、小さいけど「ヒスイ輝石岩」と言った方が良いかも。
ビー玉は…、黄色は珍しいので拾いました(笑)
ロディン岩は鶯石ではなくアケビ石でもないタイプ、緑が入っていてヒスイに似ていますが翡翠輝石は見られません。(でも光るのでサンプルとして磨く)
緑色石英(キツネ石)は通常タイプ、茶色の部分が少ないので少し磨けば綺麗になります。
オンファス輝石は非常に滑らか、この時点でツルツルのピカピカなので容易に艶が出ます。
このまま磨いて「小さな飾石」として活用したいと思います。
戻りながら探していると、次第に大きな雲が空を覆い太陽を隠し始めました。
ちょっと残念…、でも暖かいので、もうしばらく探石を楽しみます。
そんな中で見付けたのはオンファス輝石、石英斑岩、泥岩砂岩互層?です。

オンファス輝石は大きくて良質、文鎮にするか加工素材にするか迷うサイズです。(色が濃いので石質が安定している)
石英斑岩は通常とは違い赤色を示すタイプ、茶色よりは少ないですが、だからと言って稀少とまでは言えません。(でも模様が綺麗な赤色タイプは珍しいかと)
この色の違いは何なのだろうか?、どちらも同じく鉄分の沈着によるものなのかな?
泥岩砂岩互層?は自然の箸置きみたい(笑)、でもちょっと箸には大きいので筆やペンを置く方が良いのかも。(棒状なら大抵の物は安定するでしょう)
最後は蛇紋岩?1個、ネフライト1個、玉髄2個、ヒスイ転石1個です。

蛇紋岩?はアンチゴライトなのかな?、濡れているとネフライトと間違えますが、硬度が違うので乾いた時のパサつきも強く出ます。(よって硬度が低い)
蛇紋岩ではなくて閃石類なのかな?、磁石で確認できるようですが、どんな磁石でも良い訳では無かった気がしたのですが…、忘れました(笑)
ネフライトはさっきのより良質、磨けば手触りも良くなるのでツボ押しに使ったりします。(私が使っているだけですが)
玉髄は白い縞模様が見られるので縞瑪瑙と言えるでしょう。
未だに理想的な活用法を見出せていませんが、なんであれ磨いてみます。
ヒスイ転石は黒ヒスイに分類するタイプ、濃い灰色だから灰色ヒスイでも良いのかも?
黒ヒスイは海岸転石としては珍しく、色的にも目に付きにくい事が影響しているのでしょう。
色で言えば青は稀少、ヒスイじゃないけどピンクも珍しい。
ちなみに疑問なのは、ピンクゾイサイト(灰簾石)の小さい転石が見当たらない事です。
ヒスイ・ロディン岩・玉髄はあるのに、ピンクゾイサイトの小さな転石は滅多にないです。
でも大きな原石は幾つかあって、稀少ではあるけど持っている人も多いです。(ピン〜キリですが)
川で砕けないのかな?、それとも砕けたら海へ出るまでに粉々になるのかな?
硬度の低いボーウェナイト(蛇紋石)と同じ理由なのだろうか?、それが解ったから何なんだって話ですが疑問には思います(笑)
そんな事を考えながら右側に到着、青空は広い雲に覆われてしまい残念。
浜は見るからに砂だらけ、疲れたし気分も乗らなかったので探さずに帰りました(笑)

最近は現実…、いや幻想逃避をしまくってますね…。
この現実世界(自然領域)の魅力は凄まじく、虜になってしまうのも良く解ります。
気を付けなければ海を彷徨いて終わってしますね(笑)、現実(自然領域)に向き合ったとしても豊かに生きられないなんて、人間ってのは「半端な生き物なのだな」と思います。(中途半端に向き合うからかな?)
そう言えば「石の力」について質問される事が多くなっているそうです。
特に「薬石」などに多いようですが、私個人の考えとしては石に力はあります。(当然だが)
でもそれを感じられない人もいるし、なによりも根本を理解していないので説明が面倒で難しくなります。(短時間では無理かと)
よって「人間に力が宿っている」とした方が手っ取り早いです。(これも事実ですから(笑))
人間と言うものは基本的に弱く、必ず誰かの責任・何かの責任にして自己を守ろうとします。
なので石に力を感じられない人は「石に力が無い」って結論を出して納得しようとするのですが、そもそもに「人間に都合の良い効果」なんて神(自然)は創りません(笑)
都合の良い事だけを「力」とするので本質から逸れるのですよね…。
人間が自然から特別な力を得られる方法は一つ、面白いと思う感性・美しいと思う感性、これらの感動を自身の活力に変えて身体に適応させる事です。(ある程度は本能で行われている)
普通に「そうやって進化してきたんだろうが」って思う、何故こういった感性が人間に備わっているのか考えた事はないのだろうか?(現実逃避の究極体なのに…)
逃げに逃げて現実逃避しまくった人類が自然(神)から力を得る方法、それは逃げてきた相手(領域)の素晴らしさを認識して体内の細胞を活性化させ、脳内の血液を回し五感を研ぎ澄まし、自然(神)の産物でもある人類の奥底から力を呼び起こす、それが「人間にとって都合の良い効果」をもたらす仕組みと言えます。(後は薬や健康食品のように成分を分析して、人間に都合良く作り変える方法しかない)
とにかく「人間に力が宿っている」って事を強調すれば、責任は鉱物にはなく、人間(と言うか個体)の責任になります。
要は「引き出せない程の脆弱な感性」と「奥底の無い浅すぎる魂」、これが原因なので鉱物が責められる道理がないわけです。
人間として生まれたのならば、「人間としての性能をフル活用してみせろ」って事ですね(笑)
しつこく言いますが「人間に都合の良い効果なんて神(自然)は創らない」ので、自然に文句を言っても無駄です。
他者に文句を言うのは勝手ですが「適応できる者にしか向けていない」って事実があるので、まずは自分の性能を知るところから始めると良いかと思います。
これは神社仏閣も一緒、テーマパークの原点なのだから人が集まるのは当然だし、より人にやさしい存在として神仏が創られたのも道理、全ては人間が求めた結果なのだから。
現実と幻想をリンクさせる事で「願いを叶える力を備える」のは人間の特権でもあるし、その未来をカタチにするのは本人次第です。
結論として石にも人にも力は宿っていて、それらが魅力(引力)により引き合う事で活力となるわけですね。
一方的に力が発動するのではなく「活力になる」って事で、良い結果を出すには自分で乗り越えるしかないです。(人間の都合は人間で良くするしかない)
基本はこんな感じで思っていれば良いかと思います、でも運命的な出来事など説明の付かない浮世離れした事もあるので、それを体験したのなら難しく考えなくても良いかと思います(笑)
現実領域では生物、幻想領域では人間、この事を理解すれば「力の存在」を知るでしょう。
ちなみに仮想空間は基本ゴミ箱なのですが、そこから「資源を得る者」と「ゴミをあさる乞食」とに分かれます。
この違いは明確にされていませんが、時代が進むに連れて解りやすくなるでしょう。
次は価値についての話になりますが、希少性が高ければ価値が高いのか?、と問われると否でしょう。
それぞれの人間の魂は一つ一つ違っていて稀少だと言えますが、同じ価値ではありません。
何故かと言えば「面白くもなく、美しくもないから」ですね(笑)
よって価値を高めたいのなら希少性だけではなく、面白さ・美しさなどの「魅力」を高める必用があります。(人間にとっての万物の真理かと)
まぁ、「価値を高めたいのならば」の話なので、人間は普通に生きていても幸せにはなれます。(人間の魂を比べたって一銭にもならないし(笑))
でも、「ものづくり」で生きる人たちには「魂の質量を高める事」は不可欠になるでしょう。(商品〜作品を売って生きるのだから)
これが現段階での私の答え。(問われていませんが勝手に答えてみました(笑))
これからの人生でもっと深く知る事になるでしょうから楽しみです。
今回は盛大に話が逸れましたが、これで今回の探石記録は終わります。